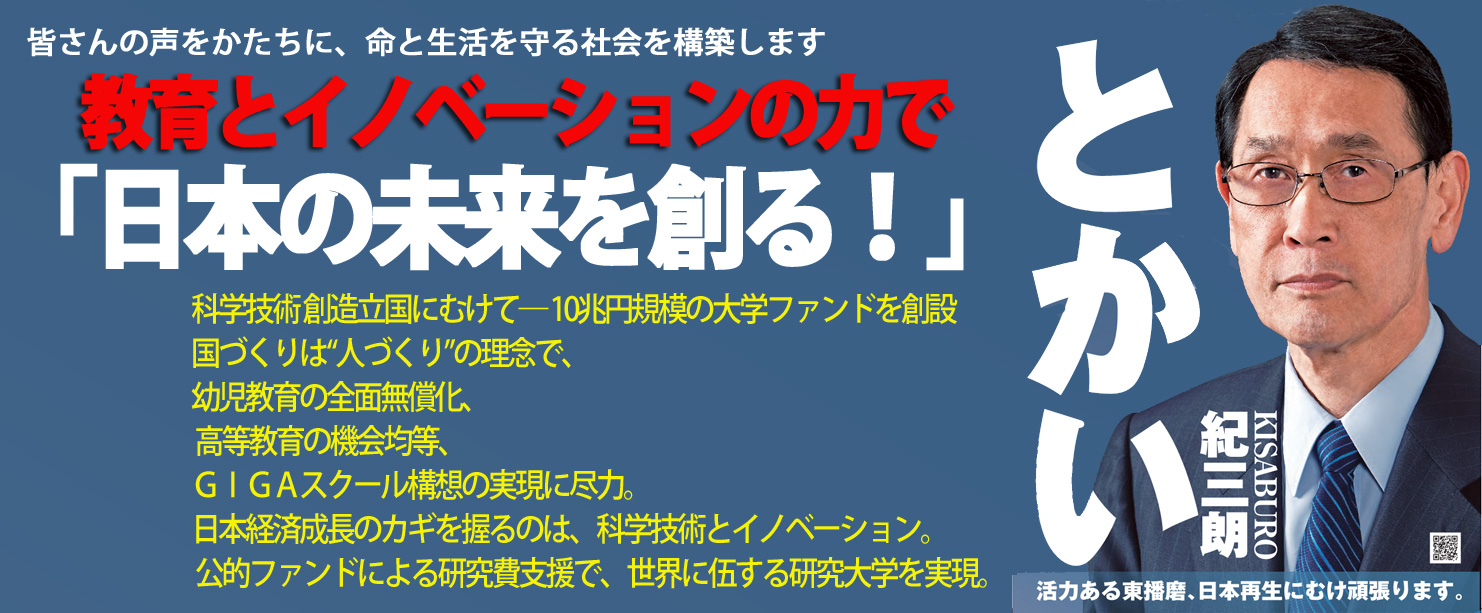通常国会も会期末まであと一月足らず。平成25年度予算は成立したものの、審議中の重要法案は山積しており、まだまだ過密スケジュールで本会議、委員会が開催されている。
先週、その合間を縫って、国立劇場で文楽(人形浄瑠璃)を楽しませてもらった。といっても私に文楽鑑賞の趣味があるわけではなく、政界でもっとも親しい友人の誘いで観劇の機会を得たものだ。
出し物は「一谷嫩軍記(いちのたに ふたば ぐんき)」。須磨、一ノ谷で繰り広げられた源平合戦の有名な一場面。若き公達平敦盛と源氏の武将熊谷次郎直実の一騎打ちが素材だ。息子と同年の敦盛を討たざるを得なかった直実の悩みと出家の真相を扱ったもので、題名は敦盛と直実の一子小次郎、二人の若武者を若木の双葉にたとえている。
作品は史実とは違った観点で構成されているが、子を想う二人の母親の心情や武士としての生き方に無常を感じる直実の姿は、観る者の心を揺さぶる。
「退屈かもしれないが、せっかくの機会だから一度観てみるか」という軽い気持ちで、国立劇場へ足を運んだ私だったが、いつしか夢中で人形劇に魅せられていた。
抑揚をつけ朗々と語る義太夫、響き渡る三味線の音色、そして3人で操る人形遣い。
人形の綾なす姿(しな)は生身の人間以上、曰く言いがたい色気を感じた。退屈するどころか、ぐんぐん劇中に引きずり込まれていく自分がいた。やはり、本物を見なければ感動は伝わらない、臨場感(現場)を大切にしなければならないと、つくづく反省した次第だ。
文楽を巡っては昨年の夏、橋下徹大阪市長が「人形劇なのに(人形遣いの)顔が見えるのは腑に落ちない」とか観客動員の努力不足などを指摘し、文楽協会に対して市の補助金凍結を突然言い出し物議をかもしたのを覚えている方も多いだろう。
文楽は、文禄・慶長年間(1592~1615)頃から発展してきたと言われている。私は400年に及ぶ文楽の伝統はしっかり守っていかなければならないと思う。文楽だけではない、歌舞伎にしろ、能にしろ、我が国の伝統ある舞台芸術は、庶民の暮らしの中で娯楽として生まれ、それを芸として高めつつ、今日まで引き継がれてきた文化である。
この文化を私たちが後世に引き継いでいくために、今の文化行政のあり方を改める必要があるのかもしれない。とかく古典的な舞台芸術というと、「専門家でないと理解できない、解説がなくては素人にはわからない」、というように思いこまれている(私もその一人だった)。 しかし、芸術の素晴らしさは、一人ひとりの体感で感じるものだ。学者がすばらしいと言うから優れているのではない。
今回の初観劇を通じて、文楽は間違いなく守るべき伝統芸術であり、文化だと私は確信した。
芸術文化を振興するには、第一に、国民誰もが“本物”の芸術を体験できる機会を提供しなくてはならない、子どもたちが“本物”に触れる芸術体験教育を実施しなくてはならない。これも文部科学行政が取り組むべき、新たな分野である。
誰もが生き甲斐に満ちた成熟社会に向けて、政策課題は尽きるところがない。