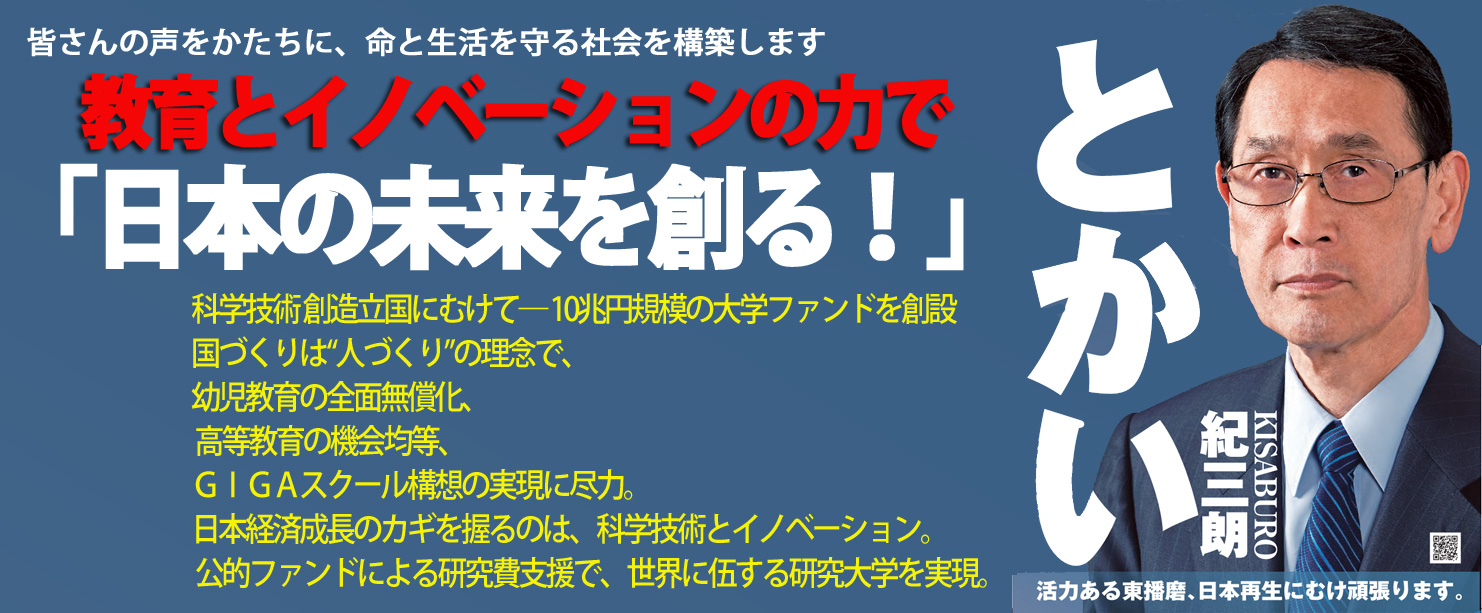地球の環境に最も近い惑星である「火星」は、今や世界各国が新発見を競い合う探査ラッシュの様相を呈している。先行していたアメリカ、EU、ロシア、インドに続き、今月9日には日本のHⅡAで打ち上げられたUAEの探査船も周回軌道に入った。
そして、19日朝には「忍耐」を意味する「パーシビアランス」と名付けられたアメリカの新型探査車が火星に着陸した。昨年7月にフロリダから打ち上げて以来7か月、4億7千万キロを旅し、かつては湖だったと考えられている「ジェゼロ・クレーター」という地点に降り立ったのだ。先輩探査車「キュリオシティ(好奇心)」と同様に、これから2年間、数十キロを走り周って探査を続ける。その名のとおり根気強くコツコツと火星の地中を調べ、微生物が存在する(した)ことを確認してもらいたい。
この探査車の開発には、NASAの研究所に勤務する日本人エンジニア、大丸拓郎さん(31)が参加している。大丸さんは着陸が成功した直後にNHKの取材に答え「無事に着陸してほっとしたが、これからが本番なので、厳しい環境の火星で探査車が計画どおりに動いてほしい」と語っている。今回のプロジェクトでは、搭載された小型ヘリコプターで、火星の薄い大気の中での飛行試験に挑むほか、将来、地球に持ち帰ることを前提にドリルで地質のサンプルを採取することも計画されている。
大丸さんは「明るい話題がない中、火星探査機は希望を与えてくれる象徴のような存在。生命の痕跡を見つけられれば、人類にとって大きな発見になる。注目してもらえればとてもうれしい」とも話されていた。
思い起こせば、幼いころの私はロケットを作ることを夢見ていた。宇宙工学を専攻しMITに留学してNASAで仕事をしたい、などと言っていた時期があった。そういうに考え至った理由は定かでは無いが、アポロ計画が影響したことは間違いない。中学時代の私はアメリカの若き大統領、ジョン・F・ケネディに憧れ、1962年9月12日に国民へ向けて行われた演説の一説、“We choose to go to the moon(我々は、月に行くことを決めました)”というくだりにとても感動した記憶があるのだ。
残念ながらケネディ大統領は、その演説のわずか1年後に暗殺され、自分の目でアポロ計画の実現を目にすることは叶わなかった。しかし、無謀にも思えた「10年以内の有人月面着陸」という夢のような公約は1969年7月16日に確実に達成された。
半世紀たって我々は、我が国発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来の延長にないより大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発を推進する新たな制度を創設、「ムーンショット*」と名付けた。
私の人生は、かつての夢とは全く異なる方向に進んだが、今回のような“宇宙開発”に関する報道に接すると、今でも未知への挑戦を繰り広げている科学者を羨ましいと思うことがある。今般のコロナ対策でも明らかなように、国民への説明責任を果たす上で、政策決定には科学的知見に基づくエビデンスが必須でもある。科学者にはなれなかった私ではあるが、これからも政策形成のプロセスで科学に関わっていきたいと思う。
追伸:20日の夕刻、オーストラリアから「大坂なおみ全豪オープン優勝!」という素晴らしいニュースが飛び込んできた。五輪組織委員会を巡る問題を吹き飛ばすような、彼女のパワフルなプレーと笑顔の優勝スピーチは、改めてスポーツが持つ力を実感させてくれた。今夏のオリンピックでも大阪選手の大活躍を観られるためにも、まずはコロナウイルスの感染終息に向け万全を尽くさなければならない。
*ムーショット目標(2050年までに)
目標1 人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現
目標2 超早期に疾患の予測・予防することができる社会を実現
目標3 AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現
目標4 地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現
目標5 未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・ムダのない持続的な食糧供給産業を創出
目標6 経済・産業・安全保障を飛躍的に発展させる誤り耐性型汎用量子コンピュータを実現
目標7 主要な疾患を予防・克服し100歳まで健康不安なく人生を楽しむためのサステイナブルな医療・介護システムを実現